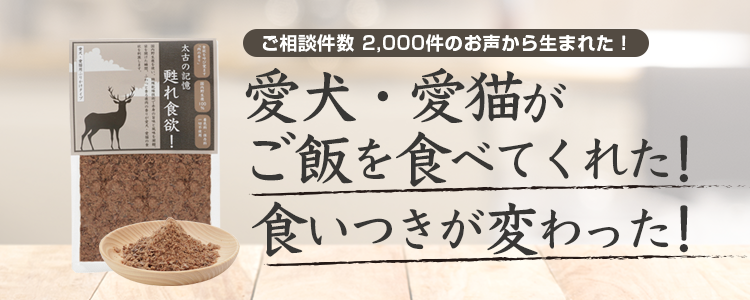愛猫が急にご飯を食べなくなると、病気ではないかと不安になってしまいます。猫の食欲不振は、体調不良や病気だけでなく、フードの「食べ飽き」や嗜好性の低さ、フードボウルの形状など、さまざまな原因で生じます。
愛猫が急にご飯を食べなくなると、病気ではないかと不安になってしまいます。猫の食欲不振は、体調不良や病気だけでなく、フードの「食べ飽き」や嗜好性の低さ、フードボウルの形状など、さまざまな原因で生じます。
本記事では、ご飯を食べない時に様子を見て大丈夫な日数や猫の食欲不振の原因を判断する基準と、原因別の適切な対処方法について解説します。
何日くらい食べなくても大丈夫なのか?
 猫には、食べたい時に食べたい量だけを取るという習性があります。そのため、食べ方にムラが生じることは少なくありません。1食分のご飯を食べなかったり残したりしても、1日単位で十分な量を食べていれば、食欲不振だと考える必要はありません。
猫には、食べたい時に食べたい量だけを取るという習性があります。そのため、食べ方にムラが生じることは少なくありません。1食分のご飯を食べなかったり残したりしても、1日単位で十分な量を食べていれば、食欲不振だと考える必要はありません。
ご飯を食べる量の減少や食べない状態が続く場合は、何らかの原因によって食欲不振が生じていることになります。
様子を見て大丈夫だとされる期間は、猫の月齢・年齢によって異なります。月齢・年齢別の様子見可能な時間は、下表の通りです。
| 猫の月齢/年齢 | 様子見可能な時間 |
|---|---|
| 1~2ヶ月齢 | 8時間以内 |
| 2~3ヶ月齢 | 12時間以内 |
| 3~4ヶ月齢 | 16時間以内 |
| 1歳以上 | 24時間(1日)以内 |
持病などがない健康な猫であれば、上記の時間内でご飯を食べなくても、特に心配する必要はありません。様子見可能な時間を超えてもご飯を食べない状態が続く場合は、動物病院の受診をお勧めします。
猫のライフステージ別の食欲不振については、以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。
ライフステージ別の猫の食欲不振
子猫がご飯を食べない!離乳後の子猫の食欲不振
老猫がご飯を食べない!高齢期の食欲不振の原因と対処方法
食欲不振があってもなくても激しく嘔吐を繰り返す、何かを食べた後にけいれんを起こす等は緊急です。病院に連絡し指示を仰ぎましょう。
絶食が36時間(1日半)続くなら病院へ
まったくご飯を食べない状態が36時間(1日半)を超えて続くようであれば、早めに病院を受診することをお勧めします。
特に太った猫の場合、絶食状態が36時間(1日半)を超えると、肝臓に脂肪がたまる脂肪肝(肝リピドーシス)になるリスクが高くなるので、要注意です。脂肪肝を発症すると、衰弱や黄疸が出るといった症状が急激に起こります。「まだ大丈夫」と思わず、絶食が許されるのは36時間(1日半)までと考え、できるだけ早く獣医の診察を受けましょう。
食欲不振以外に症状がある場合は病気の可能性も
 食欲不振だけでなく、同時に普段と違った様子や症状が見られる場合は、何らかの病気になっている可能性が疑われます。ご飯を食べない猫の様子がいつもと違う時は、早めにかかりつけの動物病院を受診すべきでしょう。
食欲不振だけでなく、同時に普段と違った様子や症状が見られる場合は、何らかの病気になっている可能性が疑われます。ご飯を食べない猫の様子がいつもと違う時は、早めにかかりつけの動物病院を受診すべきでしょう。
病気による食欲不振で生じる主な症状には、以下のものがあります。
口臭やよだれ、食べる時に痛がる
食べる時に痛がる様子が見られる時は、歯肉炎や歯周病といった口内の病気が食欲不振の原因になっていると考えられます。口臭やよだれの増加などの症状が出ることもあります。
2歳以上の成猫の8割以上が、歯肉炎という口のトラブルを抱えていると言われています。悪化した歯肉炎では、食べたくても口内が痛くて食べられなくなり、出血することも多くなります。
歯肉炎や歯周病の予防・早期発見のために、子猫の頃から口を開けることや歯磨き、口の中を触られることに慣らすようにして、歯石の付きにくい食事を選ぶようにしましょう。
嘔吐
猫は全身を舐めて毛づくろいをするので、その時に飲み込んだ毛が胃の中に溜まってしまい、毛玉として吐くこともあります。 そういったことから比較的、猫が吐くのを見ることが多いため軽視しがちですが、たとえ毛玉であったとしても、頻繁に吐くことは通常ではありません。激しい嘔吐を繰り返す場合は重篤な病である可能性があります。早めに獣医師に相談されることを強くお勧めします。 また、獣医師に正しく診断してもらうために、嘔吐の状況やタイミング、吐いた物を写真に撮るなど正確な情報を伝える事が大切です。
排尿をしない
食欲不振時に排尿がない、元気がないといった変化が見られる場合は、尿路閉塞などの重い病気が疑われます。すぐに動物病院を受診することをお勧めします。
下痢
腸の病気や感染症などさまざまな原因で、下痢が生じます。便に血液が混ざっている、脱水症状が見られる、中毒の可能性があるような場合は、重篤な病変が疑われます。できるだけ早く病院に連絡しましょう。
水を飲まない
水は動物が生きていく上で必要不可欠なものです。体内の水分が10%失われると重篤な症状が現れ、脱水状態が長く続いてしまうと、命の危険にさらされます。
普段ウェットタイプのフードを食べている猫は、フードである程度の水分を取っていますが、食欲不振になった時には、栄養だけでなく水分補給もできなくなります。
猫の皮膚をつまんで、すぐ戻らない場合は脱水症状を起こしており、さらに悪化すると目がくぼんでしまいます。脱水症状が見られ、それでも水や食事を取らない場合は、早めに動物病院を受診して水分・栄養補給をしてもらう必要があります。
食欲不振以外にも気になる変化や症状が見られる場合は、なるべく早くかかりつけの動物病院を受診しましょう。
病気以外の食欲不振の原因と対処方法
健康な猫がご飯を食べなくなる主な原因には、以下の3つがあります。
- 「食べ飽き」が生じている
- 猫の嗜好性が低いフードを与えている
- 猫がストレスを感じる形状のフードボウルを使用している
それぞれの原因別に、有効な対処方法をご紹介します。
フードの匂いを強めて「食べ飽き」を解消する
動物病院を受診して異常は見られなかったけれども、ご飯を食べない状態が続く場合に考えられる代表的な原因は、フードの「食べ飽き」です。
「食べ飽き」による食欲不振を解消するには、フードの匂いを強くすることが効果的です。猫は食べ物の匂いによって、食べるかどうかを判断すると言われています。フードを人肌程度に温める、匂いの強いフードを与えるといった方法を試してみましょう。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
キャットフードのニオイが原因?猫がご飯を食べない時は
2,500件以上の愛犬・愛猫の食欲不振に関するご相談の声から生まれた「ふりかけ」食欲を呼び覚ます鹿肉の「匂い」
当サイト「ネイチャーライフ」には愛犬・愛猫がご飯を食べてくれないというご相談が、毎日のように寄せられています。その数は2,559件に上ります(2023年8月現在)。 ペットの食のプロである私たちは、毎日飼主様と悩みを共有する中で、愛犬や愛猫にストレスを与えることなく、食欲を改善する方法を追求してきました。そして「体によいもの」を毎日喜んで食べてもらえ、飼主様の負担にならない 手軽さというコンセプトを追求し、フードにトッピングする「太古の記憶 甦れ食欲!ふりかけタイプ」を開発しました。国内野生鹿を原料とし、特殊な乾燥技術を採用して旨味や風味を損なうことなく、商品化を実現。袋を開けた瞬間にふわりと香る鹿肉の匂いが、愛犬・愛猫の食欲を刺激します。
猫の嗜好性が高いキャットフードに変えてみる
キャットフードの匂いを強めても食欲不振が改善しない場合は、フードが猫の好みではない可能性があります。
猫がフードを好んで食べるかどうかの指標を「嗜好性」と呼びます。食いつきが良い場合は嗜好性が高く、逆に悪い場合は嗜好性が低いことになります。
嗜好性には、匂い・味・食感などの要素があります。その中で、猫が最も重視するのは匂いです。嗜好性の高いフードを選ぶ際には、そのフードの匂いに注目しましょう。
嗜好性から最適なフードを選ぶポイント
以下のポイントを踏まえて、愛猫に合ったフードを選びましょう。
- 匂いが強い 一般的にドライフードよりもウェットフードのほうが、匂いが強いです。
- 猫の好みに合った味 愛猫の好みの食材(鶏肉、魚など)を理解して、好みに合ったフードを選びましょう。
- 食べやすい ドライとウェットのフードタイプに加え、粒の大きさや形によっても食べやすさや食感が変わります。
猫がストレスを感じないフードボウルの使用
 猫がエサを食べる時に、フードボウルの縁にヒゲが触れて刺激されると、猫がストレスを感じてご飯を食べなくなることがあると報道されました。
猫がエサを食べる時に、フードボウルの縁にヒゲが触れて刺激されると、猫がストレスを感じてご飯を食べなくなることがあると報道されました。
「ヒゲ疲れ」と呼ばれるこのストレスを猫が感じていると、以下のような行動が見られることがあります。
- フードがたくさん盛られている時だけ食べる。
- ボウルの中に手を入れてフードを掻き出して食べる。
- ボウルの底や縁にキャットフードが残っていることが多い。
ヒゲ疲れが疑われる場合は、ヒゲが当たらない形状のフードボウルを試してみましょう。
猫が快適にご飯を食べることのできるフードボウルの条件としては、以下のようなものが挙げられます。
- 滑りにくい
- ひっくり返らない
- 食器の高さが体格に適している
- いつも清潔に保たれている
ヒゲ疲れを防ぐことのできる、以下のようなフードボウルも販売されています。
ヒゲのストレスを解消するフードボウル
猫がストレスなくご飯を食べられるように「猫工学」に基づいて開発されたフードボウル。浅く広い形状で、容器の縁にヒゲが当たることを防ぎます。滑り止め付きで、食事中に食器が滑ることもありません。
まとめ
本記事では、猫がご飯を食べない時に様子を見て大丈夫な日数や、病気や食べ飽きといった食欲不振の主な原因と有効な対処方法について、具体的に解説しました。 持病のない健康な猫の場合は、食事を与える方法を工夫することで、食欲不振が解消されるケースも多く見られます。持病のある猫や高齢猫の場合は、食欲不振以外に気になる体調の変化がないかをチェックし、普段と違う様子があれば、早めに動物病院を受診することをお勧めします。
やっぱり食べてくれない場合
健康にも問題がなく、色々対策を練ってみたけど、それでもご飯を食べてくれない。そんな時は当サービスにご相談ください。 アドバイザーが直接状況をお伺いいたしますので、次のことをあらかじめご確認ください。
- 猫種、年齢、性別、体重、去勢・避妊手術の有無、性格
- 使用しているフード名・おやつ
- 1日のフードの量と与え方
- 使っている薬またはサプリメント等
- いつから(どんな状況で)食べなくなったか
- これまでに試したこと
- 獣医師の診断の有無
- 飼育環境(室内or屋外、冷暖房、留守番の時間など)