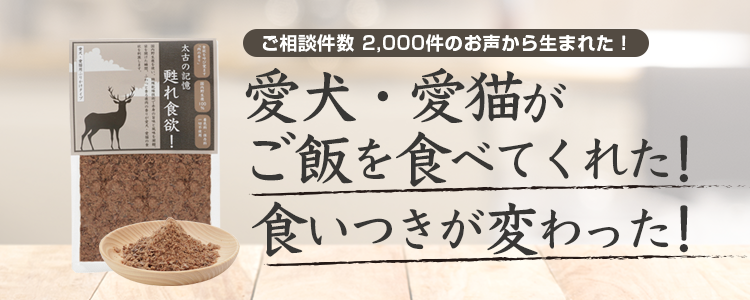急に愛犬がご飯を食べなくなった場合、様子を見ても心配のない日数はどれくらいでしょうか?また犬が食欲不振になってしまう原因としては、どのようなことが考えられるのでしょうか?
急に愛犬がご飯を食べなくなった場合、様子を見ても心配のない日数はどれくらいでしょうか?また犬が食欲不振になってしまう原因としては、どのようなことが考えられるのでしょうか?
本記事では、犬が食欲不振になった際に様子見で大丈夫な日数の目安と、病気をはじめとする原因別の適切な対処方法をご紹介します。
食欲不振と併せて普段と違う様子(嘔吐・下痢・元気がない・水も飲まない等)が見られる際には、緊急を要するケースも考えられます。動物病院の受診を強くお勧めします。
何日まで様子見で大丈夫?
 まず犬がいつからご飯を食べなくなったのかを確認しましょう。
まず犬がいつからご飯を食べなくなったのかを確認しましょう。
普段と違う様子や、下痢や嘔吐といった食欲不振以外の症状が見られなければ、持病のない成犬の場合、2〜3日程度は様子見で大丈夫とされています。3日以上食欲不振が続く場合は、かかりつけの動物病院に相談しましょう。
持病のある犬や子犬や高齢犬の場合、あるいは食欲不振以外に気になる様子がある場合は、できるだけ早く動物病院を受診すべきです。
動物病院を受診する目安
- 3日以上ご飯を食べない
- 食欲不振以外の症状、いつもと違う様子が見られる
※持病のある犬や子犬や高齢犬は、早めに受診することをお勧めします。
高齢犬や子犬の食欲不振については、以下の記事を参考にしてください。
老犬がご飯を食べない!高齢期は仕方ないの?原因と対策
子犬がご飯を食べない!離乳後の子犬の食欲不振
食欲不振以外に症状がある場合に疑われる病気
食欲不振だけでなく、普段と違う様子や症状などが見られる場合は、病気になっている可能性が疑われます。ご飯を食べない愛犬の様子がいつもと違う時は、できるだけ早めにかかりつけの動物病院に相談・受診することをお勧めします。
食欲不振と同時に生じる症状別に、発症が疑われる主な病気について以下に説明します。
歯の汚れ、歯茎の腫れ、口臭
ご飯を食べなくなった犬の口内をチェックしてください。歯の汚れや歯茎の腫れ、口臭が気になる場合は、歯周病や口内炎が疑われます。半数以上もの成犬に見られると言われる歯周病は、犬が食欲不振になった場合に注意が必要な病気のひとつです。
口の中に何らかの問題が生じると、フードを食べにくくなり、食欲不振になってしまいます。歯周病や口内炎を発症すると、空腹から胃液を吐いたり、フードの匂いを嗅いだりする行動が見られますが、しっかりと口を開けて食べ物を取ることが困難になります。歯周病や口内炎を予防するために、普段から歯磨きなどのケアをするように、定期的に動物病院で口内の検診を受けるようにしましょう。
発熱、咳、呼吸困難
食欲不振と同時に、発熱や咳、呼吸困難などの症状がある場合は、寄生虫やウイルス、細菌による感染症が疑われます。子犬や高齢犬が感染症にかかってしまうと、命に関わる重篤な状態になるリスクもあります。十分に注意しましょう。
感染症には、ワクチン接種で予防できるものもあります。ワクチンの接種時期や副作用などについて獣医師に相談した上で、適切なワクチン接種を行いましょう。
下痢、嘔吐、血便
食欲不振以外に下痢や嘔吐、血便などの症状が出たり、お腹をさわると痛がったりする様子が見られる場合は、胃腸炎や胃潰瘍、腸閉塞などの消化器系の病気が疑われます。同様の症状は、異物を口にして消化不良を起こしている時にも見られます。
食欲不振に加えて、下痢や嘔吐などの症状が続く際には、急を要するケースも想定されます。できるだけ早く動物病院に連絡して、指示を受けることをお勧めします。
元気がない、ぐったりしている
食欲不振と同時に、元気がない、ぐったりしているといった症状がある場合は、心臓疾患や肝炎、腎不全といった内臓の病気が疑われます。
内臓の病気によって食欲不振が生じた時は、犬の全身状態が悪化している可能性があります。早めに動物病院を受診しましょう。
いびき、ゼーゼーとした呼吸
食欲不振時に普段と違ういびきやゼーゼーとした呼吸が見られる場合は、短頭種気道症候群などの呼吸器疾患が疑われます。症状が悪化する前に、できるだけ早く動物病院を受診することをお勧めします。
水を飲まない
ご飯を食べないだけでなく、水も飲まなくなる場合は、犬の全身状態がかなり悪化している可能性が考えられます。椎間板ヘルニアなどの激しい痛みが出る病気、進行して全身に転移している悪性腫瘍、重度の感染症による敗血症などがあると、犬はご飯も水も口にできなくなることがあります。
食事だけでなく水も飲まない状態が続くと、脱水症状を起こすリスクがあります。このようなケースでは、早めに動物病院を受診すべきです。
愛犬がご飯を食べなくなり、病気が疑われる場合は、自己判断をせずに早めに動物病院を受診しましょう。
犬の食欲不振の原因となるストレス
愛犬の精神的なストレスが、ご飯を食べない原因になっていることがあります。病気の疑いがないにも関わらず、ご飯を食べない場合はストレスを疑ってみましょう。ストレス状態であることは犬の行動や身体両面に現れ、あくび・舌舐めずり・身体を掻くなど、さらに強いストレス状態の場合は吠えたり噛んだりといった攻撃的な行動に現れます。またストレスに伴う身体症状としては嘔吐、下痢、抜け毛などが見られます。
犬がストレスを感じる代表例としては、以下のような生活環境の変化があります。
- 引越しをした。
- 留守番をさせる回数や時間が増えた。
- 散歩に出かける回数が減った。
- 新しい犬を迎えた。
心当たりがあれば、まずストレスを解消するためにコミュニケーションをとることが大切です。
留守番をする回数や時間の増加、散歩時間の減少などがある場合は、飼い主様とのコミュニケーション不足がストレスの原因になっている可能性が考えられます。散歩時間を長くするための工夫をする、愛犬とふれあう時間をできるだけ多くするなどの点に留意して、愛犬が満足できる十分なコミュニケーションをとるようにしましょう。
フードの「食べ飽き」による食欲不振
動物病院での診察で病気などの異常がないと言われ、思い当たるストレスもないのに、ご飯を食べない場合は「食べ飽き」が原因になっている可能性があります。
フードの匂いを強めて「食べ飽き」を解消
「食べ飽き」による食欲不振の解消には、フードの匂いを強めることが効果的です。犬は食べ物の匂いによって、食べるかどうかを判断すると言われています。電子レンジなどでフードを人肌程度に加熱することで、フードの匂いを強くできます。匂いの強いウェットタイプのフードをドライフードと混ぜて与える方法も試してみましょう。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
ドッグフードのにおいが原因?犬がご飯を食べない時は
嗜好性が高いフードに切り替えてみる
フードの匂いを強めても食欲不振が改善されない場合は、フードが犬の好みではない可能性があります。
犬がフードを好んで食べるかどうかの基準となる指標のことを「嗜好性」と呼びます。食いつきが良い場合は嗜好性が高く、良くなければ嗜好性が低いと考えられます。
嗜好性には、匂い・味・食感などの要素があります。その中で、犬が最も重視するのは匂いです。犬の匂いを感知する受容体は人よりもはるかに多く、例えばジャーマンシェパードの場合、人の20倍にもなると言われています。一方、味を感じる受容体は人の4分の1以下です。このことから犬はまず匂いで食べるフードを選んでいると考えられています。
嗜好性の高いフードを選ぶ際には、そのフードの匂いに注目しましょう。
2,500件以上の愛犬・愛猫の食欲不振に関するご相談の声から生まれた「ふりかけ」
食欲を呼び覚ます鹿肉の「におい」
当サイト「ネイチャーライフ」には愛犬・愛猫がご飯を食べてくれないというご相談が、毎日のように寄せられています。その数は2,559件に上ります(2023年8月現在)。 ペットの食のプロである私たちは、毎日飼主様と悩みを共有する中で、愛犬や愛猫にストレスを与えることなく、食欲を改善する方法を追求してきました。そして「体によいもの」を毎日喜んで食べてもらえ、飼主様の負担にならない 手軽さというコンセプトを追求し、フードにトッピングする「太古の記憶 甦れ食欲!ふりかけタイプ」を開発しました。国内野生鹿を原料とし、特殊な乾燥技術を採用して旨味や風味を損なうことなく、商品化を実現。袋を開けた瞬間にふわりと香る鹿肉の匂いが、愛犬・愛猫の食欲を刺激します。
加齢による食欲不振への対処方法
犬が食べるご飯の量は、加齢による活動量や内臓機能の低下などによって、どうしても減少してしまいます。嗅覚や味覚が衰えることで、食事の嗜好性が低下することもあります。食べる量が減っても栄養が十分摂取できるように、バランスのよい食事提供を心がけましょう。
高齢犬は嗅覚が鈍くなっていますので、ドッグフードを温める、お湯でふやかして匂いを強くして与える等の工夫をしてみましょう。
また、愛犬がハイシニア期(大型犬で8歳〜/小型犬で11歳〜)を迎えたら、持病などが無い場合でも、定期的にかかりつけの動物病院を受診することをお勧めします。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
老犬がご飯を食べない!高齢期は仕方ないの?原因と対策
まとめ
本記事では、愛犬がご飯を食べなくなった時に様子を見て大丈夫な日数と、病気やストレス、「食べ飽き」といった食欲不振の主な原因と対処方法を解説しました。 持病のない成犬の場合は、飼い主と犬の接し方や食事内容などを見直すことによって、食欲不振が解消されるケースが多く見られます。持病を持つ犬や子犬、高齢犬の場合は、普段から毎日の体調の変化をチェックするようにし、気になる変化が見られたら、できるだけ早くかかりつけの動物病院を受診しましょう。